こんにちは、あさです。
テレビ東京 月曜プレミア8にて
『世界!ニッポン行きたい人応援団』が放送され、
愛知県豊橋市の筆工房『筆の里 嵩山工房(すせこうぼう)』が紹介されました。
嵩山工房が作る豊橋筆は、江戸時代から200年以上の歴史があり、
墨含みが良く、すべるような書き味の、伝統工芸品です。
豊橋筆は、日本国内の高級筆約7割のシェアを誇っています。
嵩山工房の代表は、伝統工芸士の山崎亘弘さんで、
工房では筆の製作実演販売や、
筆づくりのワークショップもなさっているそうです。
今日は、そんな『筆の里 嵩山工房(すせこうぼう)』が作る豊橋筆の歴史や、
嵩山工房の最高級筆について、調べてみました!
筆の里 嵩山工房(すせこうぼう)が作る豊橋筆の歴史は?

出典:kogeijapan.com
豊橋筆の歴史は、約200年前の1804年(文化元年)にさかのぼります。
三河吉田藩(豊橋藩)の藩主が、京都の筆職人 鈴木甚左衛門を、
藩のために筆を作る御用筆匠として、招きました。

吉田城 出典:toyohashi-bihaku.jp
また吉田藩が財政難の折、下級武士の家では内職、副業として筆を作り、
土地も、山に囲まれており、筆の材料となるタヌキやイタチの毛、竹も豊富で、
入手しやすかったため、筆づくりは発展していきました。

出典:city.toyohashi.lg.jp
明治に入ると、芳賀次郎吉が、従来の芯巻筆を改良して
水筆(現在の毛筆)の製法を広めました。
芳賀次郎吉の弟子、佐野重作は、
長さやかたさの異なる毛をまぜあわせる「練りまぜ」という技法を改良し、
14年間の修行ののちに、1878年(明治11年)に神明町で開業しました。

出典:youtube.com
重作の筆は、画家、渡辺小華にも愛され、徐々にその真価が認められます。
 渡辺小華 出典:upload.wikimedia.org |
 出典:tobunken.go.jp |
弟子が20人ほどになったころ、
豊橋に立ち寄った奈良の墨商人の助言に基づき、東京方面にも販路を開きました。
1888年(明治21年)には、豊橋駅完成も幸いし、より各地方との取引も盛んになっていきました。

豊橋駅 1988年(明治21年) 出典:blog.goo.ne.jp
1902年(明治35年)には、豊橋毛筆製造組合が創立されました。
1911年(明治44年)、重作は60歳で亡くなりましたが、生涯の間に
豊橋毛筆製造組合の組合員が150人余を数えるまでに業界は隆盛し、
今日の豊橋筆の基礎が形作られました。

佐野重作の墓 出典:apec.aichi-c.ed.jp
豊橋筆は、1976年(昭和51年)に
経済産業大臣の伝統的工芸品の指定を受けます。

出典:pinterest.jp
現在、筆の生産量は、国内では、広島県熊野町に次いで2位であり、
書道家が用いる高級筆においては、国内7割のシェアを占め、
年間180万本が全国で販売されています。

山崎亘弘さん 出典:toyohashi-fude.com
嵩山工房の代表、山崎亘弘さんは、1942年豊橋に生まれ、
16歳ころから、筆づくりを親方の小川弘氏に師事され、
29歳ころ、自宅にて独立されます。
1994年、52歳頃、愛知県表彰優秀技能賞を受賞されます。
1996年、厳しい認定試験に合格し、伝統工芸士として認定されました。
1998年、『筆の里 嵩山工房』を開かれます。

出典:twitter.com
技術、功績を称えられ、数々の賞を受賞されています。
2004年 県知事賞受賞
2008年 中部経済産業局長賞受賞
2009年 功労賞(伝統的工芸品産業功労者等経済産業大臣表彰)
2013年 瑞宝単光賞叙勲
最高級筆が気になる!
嵩山工房のホームページにて、販売している筆を見てみたところ、
以下の2点が、もっとも高級な筆かと思われました。
実際に店頭に行くと、さらにさまざまな筆がみられる可能性もありそうです。
上兼毛筆 4号(赤天尾) ¥7,000 (税込)
厳選された国産の赤天馬(馬)を使用した、高級品です。
黒天尾より滑らかで、羊毛を使用しているため、墨の持ちが良いそうです。
サイズ:穂径×穂長(約5×0.8cm)
原料(穂):赤天尾(馬),羊毛
主な用途:半紙2文字から4文字
コリンスキーイタチ筆 6号(オス)¥7,000 (税込)
ハルピン産のコリンスキー(イタチ)の毛を使用しています。
毛の色も良く、弾力があるそう。
サイズ:穂長×穂径(約3.9×0.6cm)
原料(穂):コリンスキーイタチ(オス)
主な用途:半紙8文字から12文字,仮名条幅
まとめ
豊橋筆は、吉田藩下級武士の家内制手工業を始めとし、
佐野重作などの職人により、さまざまな改良が加えられて、
徐々にその真価が全国に広まっていきました。
現在は、高級筆国内シェア7割となり、
伝統工芸品として、不動の地位を誇っています。
筆の穂首に使われる動物の毛は、1匹の動物から得られる毛はごく少なく、
職人の目と手だけで選り分けられており、
毛をある程度選別できるようになるまでに、5~6年かかるといわれています。
また、全部で36ある工程も、
現在もすべて手作業で行われています。
200年の長い歴史と、職人さんのひとつひとつ心のこもった手作業に、
豊橋筆という伝統工芸品の重みを感じます。
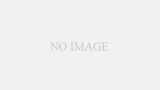
コメント